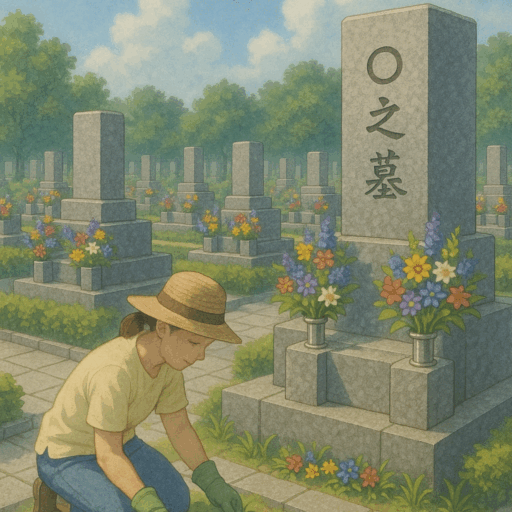墓じまいと改葬:お墓の整理と遺骨の移動を理解する

墓じまいと改葬:お墓の整理と遺骨の移動を理解する
墓じまいとは?
墓じまいとは、既存のお墓を撤去し、墓地を更地にして管理者に返還する一連の作業を指します。お墓の管理が難しくなった場合や、後継者がいない場合などに選ばれることが多く、近年では核家族化や少子高齢化により増加傾向にあります。厚生労働省によると、2022年の改葬件数は15万1076件で、過去最高を記録しています。墓じまいは単なる撤去作業だけでなく、遺骨を新しい場所に移す「改葬」とセットで行われることが一般的です。遺骨を勝手に移動したり廃棄したりすることは法律で禁止されており、適切な手続きが必要です。
改葬とは?
改葬とは、現在のお墓から遺骨を取り出し、別の墓地、納骨堂、永代供養墓、樹木葬などに移すことを指します。「お墓の引っ越し」とも呼ばれ、遠方のお墓を近くに移したい場合や、管理負担を軽減するために選ばれます。改葬には自治体の許可が必要で、「改葬許可証」を取得しなければなりません。改葬先は一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養など多様な選択肢があります。
墓じまいと改葬の流れ
親族の同意を得る
墓じまいは家族や親族にとって重要な決断です。先祖代々の墓の場合、親族全員の理解を得ることがトラブル防止に繋がります。特に寺院墓地では、檀家を離れる(離檀)ことになるため、住職に丁寧に相談することが重要です。
改葬先を決める
遺骨の新しい納骨先を決定します。選択肢には以下が含まれます:
一般墓:新たに墓石を建てる(費用:100万円~)。
永代供養墓:寺院や霊園が永代にわたり供養(費用:5万~150万円)。
納骨堂:屋内に遺骨を安置(費用:10万~100万円)。
樹木葬:自然に還る形式(費用:10万~100万円)。
散骨:海や山に遺骨を撒く(自治体の条例確認が必要)。
必要書類の準備
埋蔵証明書:現在の墓地管理者に発行依頼(費用:300円~1500円)。
受入証明書:改葬先の管理者に発行依頼(費用:0円~1500円)。
改葬許可申請書:現在のお墓がある自治体の役所で入手し、記入。遺骨1柱につき1通必要。
これらを自治体に提出し、「改葬許可証」を取得(費用:0円~1500円)。
閉眼供養(魂抜き)
墓石から故人の魂を抜く儀式で、僧侶に依頼します。お布施の相場は3万~10万円。神道では「御魂抜き」と呼ばれ、仏教とは異なる形式で行われます。
墓石の撤去と遺骨の取り出し
石材店に墓石の解体・撤去を依頼し、墓地を更地にします。費用は1㎡あたり10万~20万円。遺骨の取り出し費用は1柱あたり1万~5万円。
遺骨の移動と納骨
改葬許可証を改葬先の管理者に提出し、遺骨を納骨。新しい墓地では「開眼供養」(魂入れ)が行われ、お布施は3万~10万円が相場。
墓地の返還
更地にした墓地を管理者に返還し、契約を終了。寺院墓地の場合、離檀料(3万~20万円)が発生することがあります。
費用
墓じまいの総費用は35万~250万円で、以下に分かれます:
墓石撤去費用:10万~20万円/㎡。
閉眼供養のお布施:3万~10万円。
行政手続き費用:0円~1500円。
改葬先費用:一般墓(100万~)、永代供養墓(5万~150万)、納骨堂・樹木葬(10万~100万)。
離檀料(寺院墓地の場合):3万~20万円。
費用を抑えるには、永代供養墓や樹木葬を選ぶ、複数業者から見積もりを取る、自治体の補助金制度を確認するなどの方法があります。
神道における墓じまいと改葬
神道の墓(奥津城)は仏教の墓と異なり、シンプルで自然と調和したデザインが特徴。家紋が家系の象徴として大きく刻まれます。墓じまいでは「御魂抜き」を行い、改葬先でも神道の祭祀(玉串奉奠など)で納骨。散骨や樹木葬を選ぶ場合も増えていますが、神道の清浄さを保つため、しめ縄や榊が用いられることがあります。
注意点
親族間のトラブル回避:事前に全員の同意を得る。
寺院との関係:離檀時のトラブルを避けるため、丁寧な説明と感謝を伝える。
遺骨の状態:古い墓では遺骨が土に還っている場合、改葬許可が不要な場合も(厚生労働省通達)。
家紋の扱い:改葬先で新たに墓石を建てる場合、従来の家紋を刻むか確認が必要。家紋は家族の歴史を象徴し、特に神道では重要な役割を果たします。
現代の背景
墓じまいと改葬が増える理由は、少子化や都市部への人口集中による管理の困難さ、後継者不足です。永代供養や散骨を選ぶことで、子孫への負担を軽減する傾向が強まっています。
まとめ
墓じまいはお墓の撤去と墓地の返還、改葬は遺骨の移動を意味し、両者はセットで行われることが多いです。親族や寺院との相談、自治体の許可手続き、閉眼供養や墓石撤去、改葬先の選定が必要です。費用は選択する供養方法で大きく異なり、慎重な計画が求められます。